家を壊して家を建てることを考え始めると、解体費用はどれくらいか、新築までの流れはどうなるのか、近隣への挨拶や仮住まいはどうすればいいのかなど、不安や疑問が次々と出てきますよね。じつは、家を壊して家を建てる計画はポイントさえ押さえればスムーズに進められます。
この記事では、解体から新築までの具体的なステップ、費用の目安、注意点、補助金制度まで、あなたが今すぐ知りたい情報を分かりやすくまとめました。
初めての建て替えでも安心して進められるよう、実務経験に基づくリアルな視点で丁寧に解説していきます。
【この記事で分かること】
- 家を壊し家を建てる際に確認すべき法的条件
- 家を壊し家を建てる際の解体費用と予算の立て方
- 家を壊し家を建てる際の工事発注方法と業者選びのポイント
- 家を壊し家を建てるプロセス全体の流れと活用できる制度
家を壊して家を建てる際のポイント整理
まずは、家を壊して家を建てる計画にあたって、とくに押さえておきたい条件や準備事項を整理します。
ここを曖昧にしたまま進めると、後戻りがきかない段階で「こんなはずじゃなかった」が出てきてしまいます。
土地の条件、法令、解体費用、工事の発注方法、そして登記などの手続きまで、最初に全体像を把握しておきましょう。
家を壊し家を建てる際の再建築不可物件とは

my blog/イメージ
「再建築不可物件」は、家を壊し家を建てる計画を考えるうえで、いちばん最初にチェックしてほしいポイントです。
簡単にいうと、今は家が建っているものの、いまの法律のもとでは原則として新しく建て替えができない土地のことを指します。
接道義務を満たしているかを必ず確認
代表的な理由が「接道義務を満たしていない」ケースです。
建築基準法では、建物の敷地は原則として幅4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない、と定められています(建築基準法第43条・第42条など)。(出典:電子政府の総合窓口e-Gov「建築基準法」)
古い住宅地では、昔の細い道に面した土地や、旗竿地(道路から細い通路で中に入る形の土地)などで、間口が2mに満たなかったり、そもそも法律上の「道路」と認められていない私道にしか接していない、ということがあります。
こうした土地は、現状の家を壊してしまうと、新たに家を建てるための建築確認が下りない可能性があるのです。
再建築不可だと何が困る?
再建築不可物件になると、家を壊し家を建てるどころか、リフォームで延べ床面積を増やす増築にも制限がかかる場合があります。
不動産として売却する際にも、評価額が大きく下がったり、そもそも住宅ローンが付きにくくなるので、買い手が見つかりにくくなることも多いです。
もしあなたが「築古の実家を相続して建て替えたい」「古家付き土地を買って新築したい」と考えているなら、次のようなポイントを必ず確認しましょう。
再建築不可かどうかを確認するチェックポイント
これらは不動産会社やハウスメーカーだけに任せず、あなた自身も図面や公図・道路台帳などを見ながら確認しておくと安心です。
「売買契約前」「解体工事契約前」に確認することが大切で、解体後に再建築不可だと分かった場合のダメージは計り知れません。
法令条件は自治体や時期によって変わる可能性があります。
ここで触れている内容はあくまで一般的な考え方であり、個別の土地での適用可否は異なります。必ず最新の法令や自治体の運用を役所窓口や専門家に確認し、最終的な判断は建築士や不動産の専門家へご相談ください。
家を壊し家を建てる時の解体費用の相場と見積もり

my blog/イメージ
次に、多くの方が一番気になる「解体費用」の話です。
家を壊し家を建てると決めた瞬間から、建築費だけでなく解体費も大きな負担としてのしかかってきます。
ここを曖昧にしたまま計画を進めると、最終的にトータル予算が大幅にオーバーしてしまうことも珍しくありません。
解体費用の考え方と相場の目安
解体費用は、よく「木造なら坪5万〜8万円」「鉄骨造なら坪7万〜10万円」といった目安で語られることが多いです。
ただし、これはあくまで“平均的な条件の一例”であって、あなたの家にそのまま当てはまるわけではありません。
費用を大きく左右する主な要素は次の通りです。
解体費用のイメージ早見表(あくまで一般的な目安)
| 構造 | 延床面積の例 | 坪単価の目安 | 概算費用イメージ |
|---|---|---|---|
| 木造2階建て | 30坪(約99㎡) | 5万〜8万円/坪 | 150万〜240万円程度 |
| 軽量鉄骨2階建て | 30坪 | 6万〜9万円/坪 | 180万〜270万円程度 |
| RC造3階建て | 40坪(約132㎡) | 8万〜12万円/坪 | 320万〜480万円程度 |
※上記はあくまで一般的な相場感の一例です。地域や時期、物価、現場条件によって大きく変動します。
このように、同じ「30坪の家」でも、構造や立地条件によって解体費用が数十万円〜100万円以上変わることも珍しくありません。
ですから、インターネットに載っている相場だけを頼りにせず、必ず実際の現地を見てもらったうえでの見積もりを複数社から取ることが大事です。
見積もりで必ず確認してほしいポイント
解体の見積書を受け取ったら、次のようなポイントをチェックしてみてください。
予算には必ず“想定外費用”の枠をとして、解体費用の1〜2割程度を予備費として確保しておくと安心です。
とくに古いお家では、解体してみるまで地中や壁の中の状況が分からないことも多く、完全に予測することは難しいからです。
費用は「絶対にこの金額で収まる」とは言い切れません。
このページでお伝えしている数字は、あくまで一般的な目安です。
正確な費用は現地調査と正式な見積もりでのみ分かりますので、最終的な判断は必ず専門業者の説明を受けたうえで行ってください。
家を壊し家を建てる発注方法:一括発注と分離発注の違い

my blog/イメージ
家を壊し家を建てるとき「解体も新築も全部ハウスメーカーに任せたほうが楽?」それとも「解体業者と建築会社を分けて発注したほうが安くなる?」と迷う方が多いです。
ここでは、一括発注と分離発注のメリット・デメリットを整理してみます。
一括発注(ハウスメーカー・工務店にまとめて依頼)
一括発注は、ハウスメーカーや工務店に対して「解体〜新築まで全部お願い」という形で任せる方法です。
実際の解体作業は、その会社が提携している解体業者が行うことが多いですが、契約窓口は一つで済みます。
一括発注のメリット
一括発注のデメリット
分離発注(解体業者と建築業者を別々に依頼)
分離発注は、施主であるあなたが解体業者と建築会社を個別に選び、それぞれと直接契約する方法です。情報収集と調整の手間は増えますが、その分自由度も高まります。
分離発注のメリット
分離発注のデメリット
どちらが正解、というものではなく、あなたの時間の余裕や予算、家づくりへの関わり方によって向き・不向きが変わります。
忙しくて打ち合わせに十分な時間を割けない、多少高くても手間を減らしたい場合は一括発注が向いていますし、コストを抑えたい・自分で業者比較をしたい場合は分離発注も有力な選択肢になります。
いずれの方法でも、契約前に「責任範囲」「保証」「スケジュール」について書面で整理しておくことが大切です。
費用や体制は会社ごとに大きく違いますから、必ず複数社を比較し、最終的な判断はあなた自身が納得できる形で行ってください。
家を壊し家を建てる工事で重要な近隣挨拶とコミュニケーション

my blog/イメージ
家を壊し家を建てるプロセスでは、どうしても近隣の方にご迷惑をおかけしてしまいます。
騒音、振動、粉じん、工事車両の出入り……。
だからこそ、近隣とのコミュニケーションは「費用には出てこないけれど、実は一番大事な準備」といっても大げさではありません。
挨拶回りは「いつ・どこまで・誰が行く?」
一般的には、解体工事の1週間〜数日前を目安に挨拶回りを行います。
範囲としては、最低でも両隣と向かい、裏手の家、工事車両が通行・駐車する可能性のある家にはご挨拶しておくと安心です。
角地や袋小路の場合は、少し範囲を広げても良いでしょう。
「誰が行くか」については、解体業者やハウスメーカーの現場監督が同行してくれるケースが多いです。
ただ、施主であるあなたが一緒に回ることで「これからもご近所としてお世話になります」という気持ちが伝わりやすくなります。
挨拶回りで伝えておきたい内容
解体業者・建築業者との情報共有
近隣とのトラブルを防ぐには、現場で動く解体業者・建築業者とあなたの間のコミュニケーションもとても重要です。
例えば、次のようなことは事前に共有しておきましょう。
- 残しておきたいもの:既存の塀・庭木・井戸・記念の樹など
- 近隣の事情:高齢の方や小さなお子さんがいるお宅、夜勤の方がいるなど
- 車の出入りのルール:通学時間帯やゴミ出し時間など
- 敷地外に材料やガラを一時置きする範囲
残しておきたいものについては、口頭で伝えるだけでなく、現地でマーキングテープを巻く・写真入りの簡単な図面を作るといった形で「見える化」しておくと、担当者が変わったときにも引き継ぎやすくなります。
近隣トラブルは、お金で解決できないストレスを生むことがあります。
「ちょっとした一言」「早めの報告・相談」がトラブル回避につながりますので、気になることがあれば工事担当者に遠慮なく伝えてください。
工事中にどうしてもクレームが出てしまうこともありますが、そのときに「事前にきちんと挨拶していたか」「連絡先を渡していたか」で、相手の受け止め方が大きく変わります。
家を壊し家を建てるのは一時的な工事ですが、あなたはその場所で今後も暮らしていくはずです。長いお付き合いの第一歩として、丁寧なコミュニケーションを心がけていきましょう。
家を壊し家を建てる際に必要な滅失登記と登記手続き

my blog/イメージ
解体工事が終わると「やっとスッキリした」「新しい家のことだけ考えたい」と気持ちが行きがちですが、ここで忘れてはいけないのが登記手続きです。
とくに、家を壊し家を建てる場合は、既存建物の〈滅失登記〉と新築後の〈表題登記〉など、いくつかのステップがあります。
建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、登記簿上登録されている建物を、解体などにより「存在しなくなりました」と法務局に申請して記録を更新する手続きです。
人でいう「死亡届」のようなイメージで、そのまま放置すると、登記簿上はいつまでたっても古い家が建っていることになってしまいます。
一般的には、解体工事完了日から1か月以内を目安に申請する必要があるとされています。申請は所有者本人が行うこともできますが、多くの場合は土地家屋調査士などの専門家に依頼します。
費用は事務所によって異なりますが、数万円程度が一つの目安です。
新築後に必要な登記
家を壊し家を建てるプロセスでは、滅失登記のあとに次のような登記・手続きが続きます。
これらの手続きは、住宅ローンの実行や税金の計算にも関わる重要なステップです。
多くの場合、司法書士や土地家屋調査士がまとめてサポートしてくれますが、いつ・どのタイミングで・いくらかかるのかは事前に見積もりを取り、資金計画に組み込んでおくと安心です。
登記費用は「登録免許税(税金)」と「専門家への報酬」の2つで構成されています。
金額は建物の評価額やローン額などによって変わるため、このページでは具体的な数字を一律には示しません。
正確な金額は、必ず司法書士・土地家屋調査士からの見積もりで確認し、最終的な判断は専門家の説明を踏まえて行ってください。
登記を忘れると、後々の相続や売却で手続きが複雑化したり、住宅ローンの実行が遅れるなどの影響が出ることもあります。家を壊し家を建てる計画を立てる段階で、「解体工事の完了日」「滅失登記の予定」「新築完成と表題登記・抵当権設定」のスケジュールをざっくりメモにしておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。
家を壊して家を建てるときの流れと費用概要
ここからは「家を壊して家を建てる」ことの全体の流れと、それぞれの工程で発生しやすい費用や制度を整理していきます。
土地探しから解体、新築工事、仮住まい、補助金・税金まで、ざっくりとしたロードマップを持っておくと、今自分がどこにいて、次に何を決めればいいかが分かりやすくなります。
家を壊し家を建てるための土地探しと古家付き土地購入の注意点

my blog/イメージ
新築用の土地を探していると「古家付き土地」として売りに出されている物件を見かけることがあると思います。
これは、古い建物がそのまま残っている状態で売買される土地のことで「更地より価格が安め」「建物を壊して新築する前提」というケースが多いです。
古家付き土地のメリット
古家付き土地を選ぶ大きなメリットは、希望エリアで土地が見つかりやすくなることと、価格が更地に比べて抑えられる可能性があることです。
人気エリアでは更地がほぼ出てこない一方で、古家付きなら市場に出てくることがある、というのは珍しくありません。
また、現地で古家の中に入ってみると、日当たりや風の抜け方、窓からの眺め、近隣の生活音など、将来の暮らしのイメージがしやすい、というメリットもあります。
「ここにキッチンがあったから、うちも似た位置にしようかな」など、プラン作りのヒントにもなります。
チェックしておきたいリスクと注意点
一方で、古家付き土地には特有のリスクもあります。
家を壊し家を建てる前提で購入するなら、次のポイントは必ずチェックしましょう。
売買契約前に「解体費用の概算見積もり」を取っておくと安心です。
土地価格+解体費+新築費を合わせて、あなたの総予算に収まるかどうかを冷静に確認してみてください。
また、古家付き土地では「解体費用を誰が負担するか」が交渉ポイントになることも多いです。
売主負担で解体して更地引き渡しにしてもらうのか、買主負担のまま土地価格を大きく値引きしてもらうのかによって、実質的な総額は変わってきます。
不動産会社まかせにせず、解体費用の相場感を持ったうえで、あなたにとって有利な条件を一緒に考えてもらいましょう。
なお、契約書に「古家付き土地」「現況有姿」とだけ書かれていると、残置物や地中障害物が大量に出てきたときにトラブルになることがあります。
可能であれば「地中埋設物が大量に出た場合の費用負担」などについても事前に確認しておくことをおすすめします。
家を壊し家を建てるために必要な地盤調査・改良と費用の目安

my blog/イメージ
家を壊し家を建てるとき、意外と見落としがちなのが地盤のことです。
どんなに良い構造・良い断熱の家を建てても、地盤が弱いと家そのものが傾いたり、余計な補強費用がかかったりしてしまいます。
地盤調査の種類とタイミング
一般的な戸建て住宅では「スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)」という簡易な地盤調査が多く使われています。
細いロッドを回転させながら地中にねじ込み、沈み方の抵抗値から地盤の強さを推定する方法です。
調査費用は数万円程度が目安ですが、建築会社によっては本体価格に含んでいる場合もあります。
家を壊し家を建てる場合、解体後の更地の状態で地盤調査を行うのが基本です。
古い基礎やガラが残っていると正確な測定ができないことがあるため、解体工事と地盤調査のスケジュール調整が重要になります。
地盤改良が必要になった場合の費用感
調査の結果、地耐力が不足していると判断された場合は、地盤改良工事や、より強い基礎形式(ベタ基礎・杭基礎など)が必要になることがあります。代表的な改良方法と費用イメージは次の通りです。
- 表層改良工法:地表から数mの範囲の土をセメント系固化材などと混ぜて固める方法。費用感は数十万円〜。
- 柱状改良工法:地中に円柱状の改良体をつくって支える方法。一般的な木造2階建てで数十万〜100万円台のことが多いです。
- 鋼管杭工法など:鋼管などの杭を打ち込んで支持層まで到達させる方法。地盤がかなり弱い場合や重量のある建物で採用されることが多く、100万円以上かかることも珍しくありません。
地盤改良にかかる費用は、地質・建物の大きさ・構造・地域によって大きく異なります。このページで挙げた金額はあくまで一般的な目安であり、あなたの土地にそのまま当てはまるとは限りません。正確な金額は、必ず建築会社や地盤業者からの見積もりで確認し、疑問点は遠慮なく質問してください。
地盤改良は「できればお金をかけたくない部分」かもしれませんが、家の寿命や安心感に直結する大事な投資です。
家を壊し家を建てる計画の初期段階から「もしかしたら地盤改良で追加費用が必要になるかも」という前提で余裕をもった資金計画を立てておくと、後で慌てずに済みます。
家を壊し家を建てる際に活用できる補助金・税制優遇制度

my blog/イメージ
家を壊し家を建てるときは、解体費用・建築費用・登記費用・仮住まい費用など、どうしても大きなお金が動きます。
だからこそ、「使える補助金や税制優遇はないかな?」と探してみる価値は大いにあります。
解体工事に関する補助金の例
自治体によっては、老朽化した空き家の解体や、密集市街地の建て替えを推進するために「空き家除却補助」「木造住宅密集地域整備事業」などの名称で補助制度を設けているところがあります。内容は自治体ごとに異なりますが、例えば次のような条件が多いです。
補助金額は数十万円〜100万円程度のことが多いですが、年度予算に限りがあったり、先着順で受付が終了することもあります。
家を壊し家を建てる計画を立てたら、早めに自治体ホームページや窓口で最新の制度を確認してみてください。
新築に関する税制優遇・ローン減税
新しく建てる家については、住宅ローン控除(住宅ローン減税)や、固定資産税の軽減措置、不動産取得税の軽減など、いくつかの制度が用意されています。
制度の内容は年度や税制改正により変わるため、具体的な数字はここでは挙げませんが、次のような点は意識しておくと良いです。
補助金や税制優遇は「いつの情報を見ているか」がとても重要です。
このページで触れている内容は一般的な仕組みの説明にとどまります。
実際に制度を利用する際は、必ず国や自治体・税務署・金融機関など公式サイトで最新情報を確認し、最終的な判断は税理士や専門家へご相談ください。
家を壊し家を建てるための住宅ローン・仮住まい・引越しの手続き

my blog/イメージ
家を壊し家を建てるとき、資金面でポイントになるのが「住宅ローン」と「仮住まい・引越し」です。
新築のみのケースと違い、建て替えでは古い家のローン残債、仮住まいの家賃、引越し費用などが絡んできて、少し複雑になります。
住宅ローンの基本的な考え方
建て替えでも新築と同じように住宅ローンを利用できますが、原則として「解体する建物に設定されている既存の住宅ローンは完済しておく必要がある」と考えてください。
なぜなら、金融機関は建物と土地を担保にお金を貸しているため、担保である建物を取り壊す前に既存ローンを片付ける必要があるからです。
また、車のローンやカードローンなど、他の借入が多いと住宅ローンの借入可能額が減ってしまうことがあります。
返済負担率(年収に対する年間返済額の割合)が審査のポイントになるため、可能であれば小さなローンから順に整理しておくと安心です。
仮住まいと引越しの費用・スケジュール
建て替えの場合、今の家を壊してしまうので、どうしても仮住まいが必要になります。
一般的には、
- 旧居 → 仮住まいへの引越し(1回目)
- 仮住まい → 新居への引越し(2回目)
という2回の引越しが必要です。
家族の人数や荷物の量にもよりますが、1回あたり数十万円前後かかることも多く、さらに仮住まいの家賃・敷金・礼金なども加わります。
引越し費用や賃貸相場は、エリア・時期・業者によって大きく変わります。とくに3〜4月や9〜10月の繁忙期は料金が高騰しやすく、希望日時で予約が取りにくいこともあります。家を壊し家を建てる全体スケジュールを組むときは、「引越し業者の空き状況」も早めにチェックしておきましょう。
住宅ローンの実行タイミングや、工事代金の支払いスケジュール(着手金・中間金・完了金)との兼ね合いも、建築会社や金融機関と連携しながら慎重に組み立てる必要があります。
資金計画に不安があるときは、早い段階で営業担当者やファイナンシャルプランナーに相談し、「いつ・いくら必要になるのか」を具体的に書き出してみると全体像が見えやすくなります。
【まとめ】家を壊し家を建てることのポイント
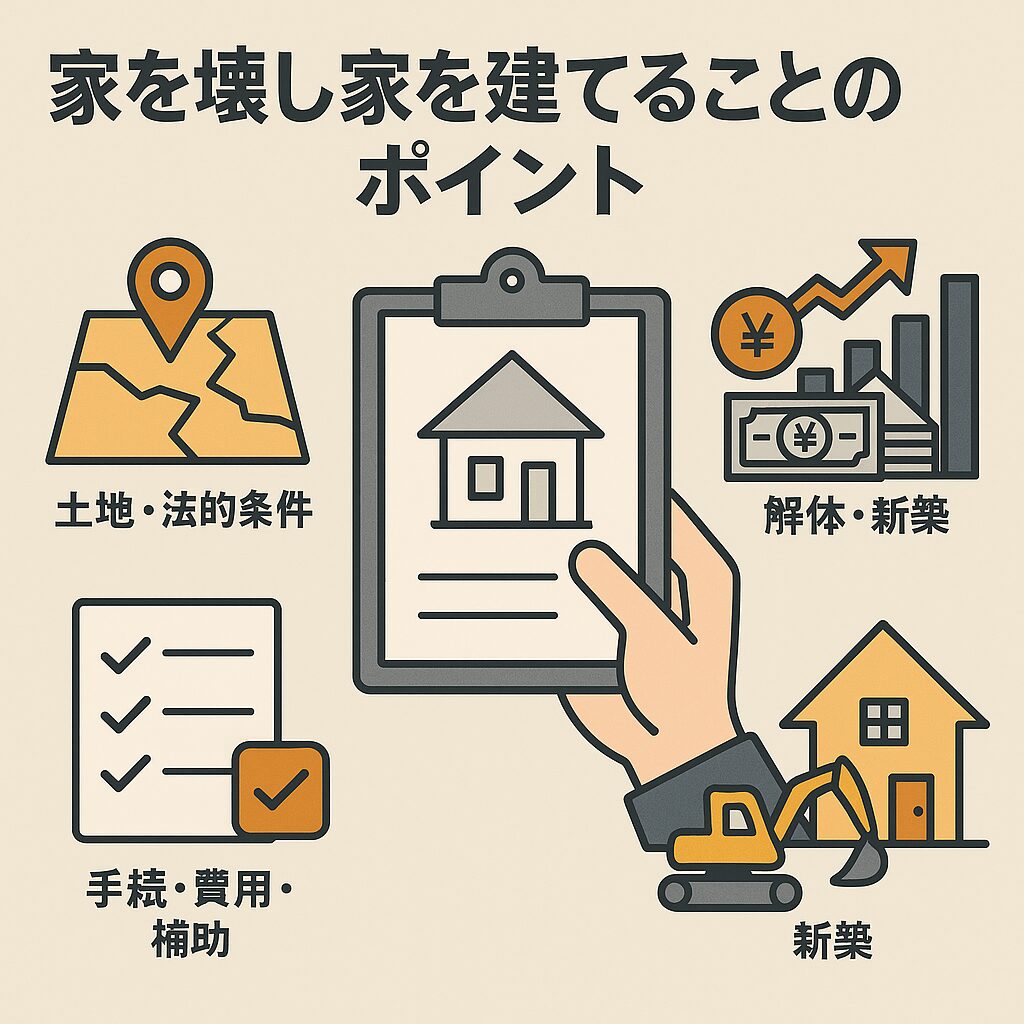
ここまで、家を壊して家を建てるプロセスについて、土地の法的条件から解体・発注方法・近隣対応・登記・地盤・補助金・ローン・仮住まいまで、かなり盛りだくさんでお話ししてきました。
一度に全部覚える必要はありませんが、次の4つの柱を意識しておくと、計画がグッと整理しやすくなります。
〈家を壊して家を建てるときの4つの柱〉
家づくりはどうしても「新しい間取りや設備」に目が行きがちですが、じつはその前段階の「家を壊して家を建てる準備」がしっかりできているかどうかで、全体のスムーズさや安心感が大きく変わります。
とくに、費用面の数字はここでお伝えしたものも含めてあくまで一般的な目安に過ぎません。
最終的な金額や条件は、必ず専門業者や公的機関の最新情報をもとに確認し、分からないことは遠慮せず質問してください。
この記事が、あなたが家を壊して家を建てるときの「道しるべ」のひとつになればうれしいです。焦らず、一つずつステップを踏みながら、理想の住まいをかたちにしていきましょう。

